ここまでやる名門会!
なぜ名門会は、難関校への合格実績を出せるのか。
名門会には、志望校合格につながる、確かな得点力を養成するノウハウがあります。
自分ひとりでは決して気付かない課題や、自分一人では決して対策しきれないことまで、徹底的に指導するのがプロ教師。
「ここまでやる名門会」。
その具体的なポイントを詳しくご紹介していきます。
得点力を鍛える
正しい過去問演習法
過去問演習STEP1
合格ラインまで、あと何点足りない?
「現在の学力」を正しく把握し、合格ラインまでの「不足」を明確に。
夢の第一志望校合格を叶えるには、確かな実力をつけることがもっとも重要です。
一方で、がむしゃらに努力し続けるだけでは、合格に手が届かない可能性もあります。
入試本番までの限られた時間を有効に使うために、まずは現状を正しく把握しましょう。
CHECK POINT
Q1. 志望校の過去問で、科目別に何点とれますか?
Q2. 志望校の合格ラインまで、(合計)何点不足していますか?
Q3. 具体的に、どの分野(単元)で失点していますか?
Q4. 具体的な失点理由は何ですか?
Q4. 入試本番まで、残された時間はどれくらいありますか?
過去問演習STEP2
どの難易度の問題を、どれくらい得点すべきか
合格戦略を立てるうえで重要な「問題難易度」。
受験生には、問題ごとの難易度を見極める力が求められます。
| 全問正解が合格の条件! 最優先で対応! | このランクの得点力が合否の分かれ道! | 手を付けるのはNG。 残りの問題に専念! | ||
| ランク | A | B | C | D |
| 難易度 | 基本 | 標準 | 応用問題 | 難問 |
| 出題割合 | 約20% | 約30% | 約40% | 約10% |
難関校の入試だからといって、すべての問題が “超難問” ではありません。
基本を確認する問題から、受験生の知識では解くことのできない問題まで、その難易度はさまざま。
難関校合格を目指すのなら、A・Bランクは絶対に取りこぼしてはならない問題です。
過去問演習STEP3
まずはA・Bランクの問題の完全解答を目指す
A・Bランクの問題で失点しているにもかかわらず、いきなりC・Dランクの対策に注力するのはおすすめしません。
基礎が固まっていない状態で高難易度の問題に手をつけても、学力として身につかないからです。
学力は一つひとつ着実に、バランスよく積み上げていくことが大前提。
残された時間を意識しながら、順序を誤らないようにしっかりと計画を立てましょう。
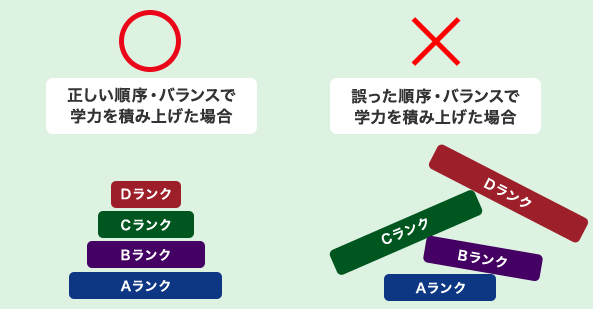
合格者の点数分布から見る
確かな合格戦略
難関校ほど1点(1問)の失点が命取りになる
難易度の高い学校ほど「受験者平均点」「合格者最低点」「合格者平均点」にそれほど差がありません。
特に最難関校の場合、受験者が合否のボーダーライン上に集中する傾向があります。
つまり、たった1~2点の差によって合否が分かれる可能性が非常に高いのです。
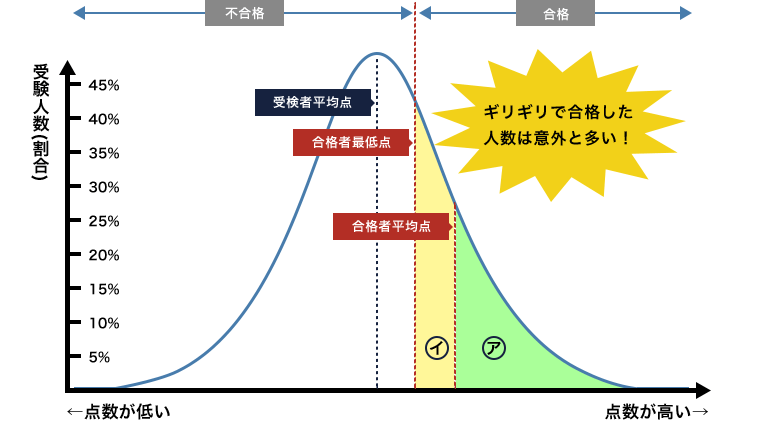
大学受験の模試におけるA判定などの判定基準は、最難関とされる医学部受験の場合、A判定からE判定までの少ない点数差の中にB~D判定がひしめき合うケースがあります。たとえE判定であっても、D判定まで残り何点なのかを精査する必要があります。
難関校は1点差で合否が変わる!受験生が心がけるべきこと
〈その1〉志望校の合格最低点は何点かを意識し、過去問演習を行う。
〈その2〉科目ごとの得意不得意に大きな差がある場合、不得意な科目での失点を最低限にとどめるとともに、得意科目で1点でも多く得点できるようにする。
〈その3〉試験によって点数が安定しない場合、どの科目のどの分野で失点しているかを見極め、1点でも多く得点できるようにする。
〈その4〉正解でなくても部分点が確実に取れるよう、問題演習を中心とした勉強で解答精度を高める。
「成績が伸びない…」
その本当の原因を見極める
表面上見えている “つまずきの原因” は、実は違うところにある場合が多いことを知っていますか。
テストで間違えた問題をただやり直すだけでは、決して成績は上がりません。
間違いの根本原因の対策をしなければ、同じ過ちを何度も繰り返すだけです。
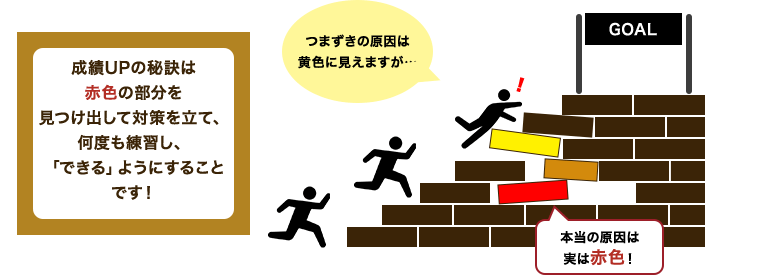
つまずきの原因を正しく見つけられるのがプロ教師。ここまでやらなければ成績は上がりません。
〈その1〉早期発見
つまずいた問題の根本原因がどこにあるのかをプロの目で見極め、確実に見つけ出します。
〈その2〉効果的な対策
見つけ出した根本原因を最短で克服するため、ベストな計画を立てて対策します。
〈その3〉反復演習
実際の問題で演習を繰り返しながら定着させ、同じ過ちが起きないよう常に目を配ります。
